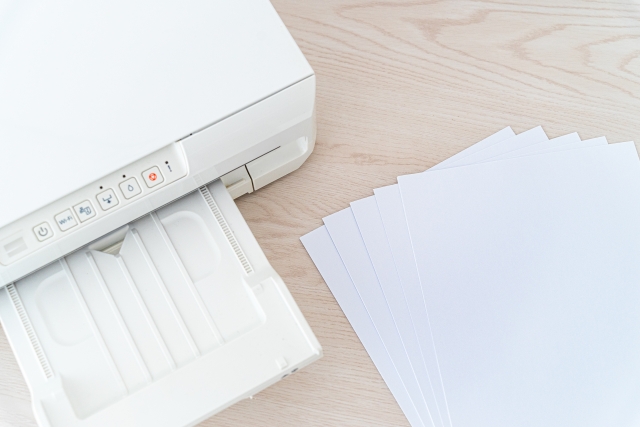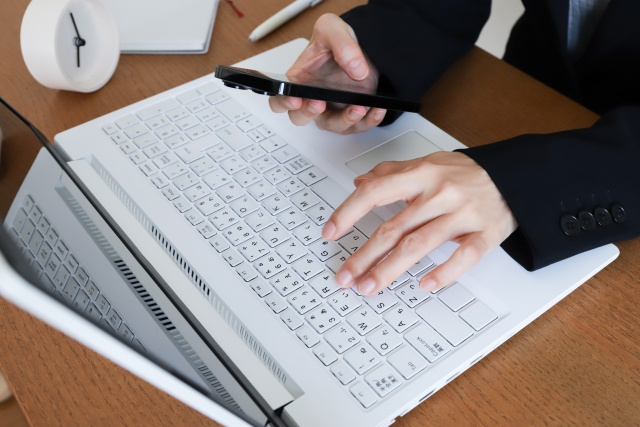「自炊」とは何か? デジタル時代の読書習慣
まず、“自炊”という言葉の意味から確認しておこう。これはもちろん料理の話ではない。ここでいう“自炊”とは、紙の書籍を自分でスキャンし、PDFなどのデジタルデータとして保存・利用する行為のことを指す。
読書端末やタブレットで本を読みたい人たちにとって、自炊は「自分の持っている本を持ち歩く」ための実用的な方法として広まった。
本を裁断し、ページをスキャナーにかけてデータ化する――この作業は想像以上に手間がかかるため、やがてその代行サービス、いわゆる“自炊代行業者”が登場することになる。
今回は、自炊代行は違法か合法か?についていくつかご紹介します。
私的利用の権利 vs 第三者の介在
日本の著作権法では、個人が自分で購入した書籍を私的にコピーする行為は、著作権の例外として合法とされている。つまり、自分でスキャンする“自炊”そのものに違法性はない。
問題は、「自分ではない誰かにその作業を頼む」場合だ。すなわち自炊代行業者にスキャンを外注すると、そこには著作権法上の「複製権侵害」の可能性が生じる。というのも、複製行為を第三者が業として行うことは、著作権者の許可が必要になるからだ。
このポイントが、“自炊代行”が違法か合法かを分ける本質である。
裁判所の判断:違法性の明確化
2011年以降、自炊代行業者に対する訴訟が相次いだ。村上春樹、東野圭吾ら著名作家が参加した「作家らによる自炊代行業者への訴訟」は特に注目を集め、最終的に東京地裁は、著作権者の許諾なく書籍をスキャンする自炊代行業は違法であると判断した。
裁判所は、「個人の私的複製は許されるが、それを代行する業者の行為は私的使用の範囲を超える」として、スキャンの主体が誰かを明確に区別した。
つまり、自炊は個人がやる限り合法だが、代行業としてスキャンを請け負うのは違法と位置づけられたのだ。
自炊代行が問う、「本の所有」と「使用」の境界線
この問題は最終的に、「本を所有するとはどういうことか?」という問いにも行き着く。私たちは紙の本を買ったとき、その“物理的な物”を所有する権利を得る。しかし、そこに書かれた“内容”――すなわち著作権的な情報は、依然として著作者に帰属している。
自炊代行は、所有と利用の境界を揺るがす行為だ。自分の持っている本を、自分のために、より便利な形に“変換”しても、それを誰かに頼んだ瞬間に違法になる。
この線引きの曖昧さに、デジタル社会における知的財産のジレンマがにじみ出ている。
図面スキャン・電子化のお悩み解決致します!
お気軽にご相談下さい!
ご相談・お見積りは無料です! 物量が多い場合は、
現地見積にお伺い致します!
019-643-8481
電話受付時間 9:00~18:00
( 土日祝除く )