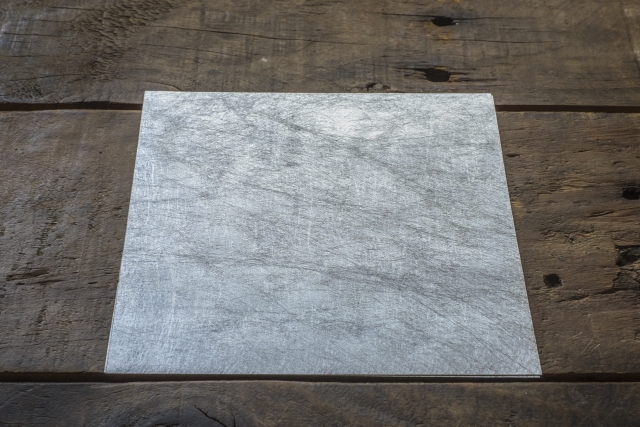地域の歴史
市役所や町役場の倉庫、資料室には都市計画の図面、議会の議事録、地域行事の記録、手書きの住民台帳、農地改革の記録といった、膨大な量の「地域の歴史」が収められている。
これらは、日々の行政運営に必要な「公文書」であると同時に、地域の営みや市民の暮らしを伝える「歴史資料」でもある。だが、紙という物理的な限界を持つ媒体であるがゆえに、劣化し、失われていくリスクは年々高まっている。こうした危機感から、自治体では今、スキャンによるデジタル化=アーカイブ化の取り組みが広がりつつある。
今回は、自治体の紙資料、スキャンの現場についていくつかご紹介します。
スキャン業務の最前線:人と機械
自治体の紙資料をスキャンする現場は、決して「スマート」な作業ではない。大量の書類の中には、古くて紙が破れかけているもの、手書きで読みにくいもの、ホッチキスや錆びたクリップが外せないもの、A0サイズの大判図面や巻物のような報告書もある。
業者委託される場合でも、「とにかく全部スキャンすればいい」という単純な話ではない。分類、整理、台帳づくり、メタデータの付与、画像の品質管理など、手間と判断を要する工程がいくつも存在する。特に、個人情報を含む文書については、慎重な扱いが求められる。
作業者の声に耳を傾けると、「一枚一枚に“地域の人生”が詰まっている感じがする」と語る人もいる。これは単なるデジタル化業務ではない。人の手によって積み上げられた記録を、人の手で未来に渡す作業なのだ。
法制度の支えと制約:公文書管理法と自治体の裁量
日本には2009年に施行された「公文書管理法」があり、国の行政文書に対しては保存・管理のルールが定められている。これに倣って、多くの自治体でも「文書管理条例」や「記録管理規程」が整備され、保存期間の分類や、廃棄と保存の判断基準が設けられている。
だが、現実には「予算がつかない」「職員の異動で継続性が保てない」「古い資料の価値判断が難しい」といった事情が重なり、スキャン以前に「何を残すか」の判断すら曖昧な自治体も少なくない。
また、スキャンしたからといって原本を即座に破棄できるわけでもない。電子化された文書の法的な証拠能力は限定的であり、公文書の原本としての保存が求められるケースも多い。つまり、スキャンは保存を補助する手段にすぎず、それだけで完結するものではない。
「紙資料」の歴史的価値と地域アーカイブの構想
自治体が保管する紙資料には、行政的な価値以上に「歴史資料」としての側面がある。戦後すぐの復興期の政策資料、昭和の都市開発の地図、合併前の旧町村の会議録などは、将来の地域史研究や住民のルーツ探索に不可欠な一次資料となる。
そのため、最近では「地域アーカイブ」という発想が注目されている。行政文書だけでなく、市民団体の記録、個人の提供資料、地元メディアの記事なども含め、地域の記憶全体を包括的に残す取り組みだ。
たとえば、ある市では住民から寄贈された古い写真や回覧板、商店の帳簿までスキャン・保存して、市民が閲覧できる「まちの記憶ライブラリー」を整備している。これはまさに、自治体と市民が協働して「地域のデジタル文化財」を築いていく試みである。
図面スキャン・電子化のお悩み解決致します!
お気軽にご相談下さい!
ご相談・お見積りは無料です! 物量が多い場合は、
現地見積にお伺い致します!
019-643-8481
電話受付時間 9:00~18:00
( 土日祝除く )