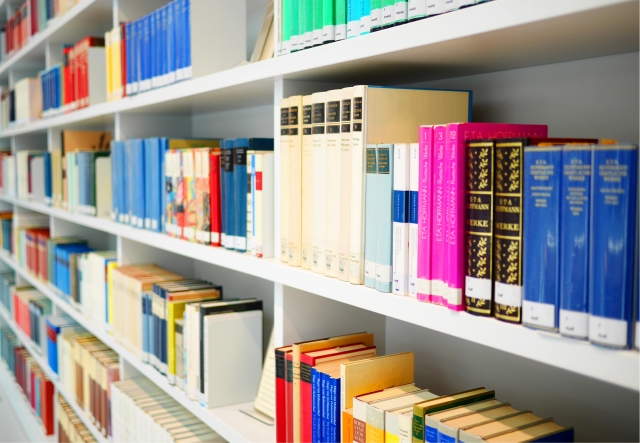便利さの先にある境界線
デジタル技術の発展によって、紙の資料をスキャンして保存・共有することは日常的になりました。業務効率化や個人の記録整理など、スキャンには多くの利点があります。しかし、「公開されていない資料をスキャンし、利用することは許されるのか?」という問題に直面したとき、どこまでがセーフで、どこからがアウトなのか、明確な線引きは意外と難しいものです。
今回は、法的側面、倫理的視点、実務での判断という3つの切り口から、慎重に考えるべき「スキャンと利用の是非」についていくつかご紹介します。
法的視点:著作権と利用許諾のあいだで
まず最初に考えるべきは、著作権法に関する側面です。著作物が公開されていようといまいと、それが創作性を持つ表現である限り、著作権は自動的に発生します。
つまり、「未公開」だからといって自由に扱えるわけではないという点は非常に重要です。
たとえば、研究機関の内部資料や未発表の講義ノート、企業の社内マニュアルなどは、それ自体が著作物である可能性が高く、たとえ入手できたとしても、勝手にスキャンして再利用・公開することは原則として著作権侵害にあたる可能性があります。
さらに、資料が未発表である場合、「著作者人格権」の一つである公表権(いつ・どのように公開されるかを決める権利)にも配慮が必要です。これは、たとえ善意であっても、本人の意思に反する形で内容が公開されると、法的リスクが発生するということを意味します。
倫理的視点:情報の信頼性と文脈をどう守るか
法律だけでなく、倫理的な観点からの検討も欠かせません。たとえば、戦前の個人日記、非公開の手紙、社内研究資料など、「記録としての価値は高いが、意図的に公開されてこなかったもの」をスキャン・利用する場合、その資料が持つ“文脈”を読み取る力が求められます。
作者や関係者が存命である場合、その意思を無視して資料を扱うことは、個人の尊厳やプライバシーを侵害する恐れがあります。また、公開されていない情報は、あくまで「非公開であることに意味がある」場合もあり、文脈を無視した引用や切り取りが、誤解や情報の歪曲を生むリスクもあります。
現代は、情報を「発見し、スキャンして、誰かと共有する」ことが容易になりました。しかしその手軽さこそが、資料に込められた背景や、人の思いを飛び越えてしまう危険性を含んでいます。
実務の視点:スキャンすべきか、しないべきか
現場での判断は、常にグレーゾーンとの対話です。たとえば、閉架書庫に眠る文献を研究目的でスキャンしたい場合、著作権者不明や連絡がつかないこともあります。また、講義資料や業務マニュアルなど、利用したいが外部への共有は明らかに制限されているものもあります。
このようなケースでは、次の3つの原則を意識することが重要です:
・スキャンはしても、外部への共有はしない(私的利用の範囲を守る)
・資料の出所・権利者を明記し、必要であれば利用許諾を得る
・判断に迷ったら、関係者に確認を取る、または使用を控える
ときには、「スキャンしておけば便利だが、使うべきではない」資料もあるということを、把握しておくことが必要です。
図面スキャン・電子化のお悩み解決致します!
お気軽にご相談下さい!
ご相談・お見積りは無料です! 物量が多い場合は、
現地見積にお伺い致します!
019-643-8481
電話受付時間 9:00~18:00
( 土日祝除く )