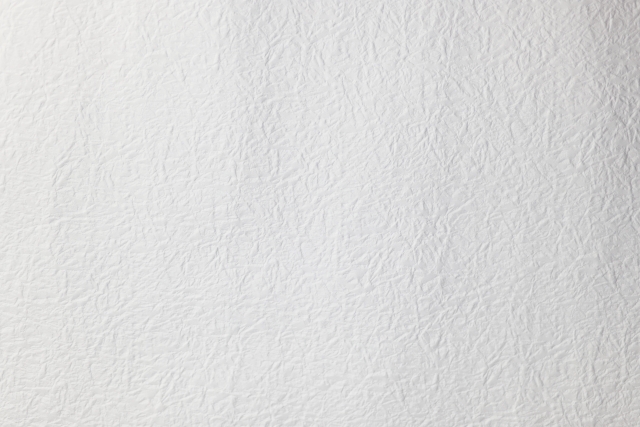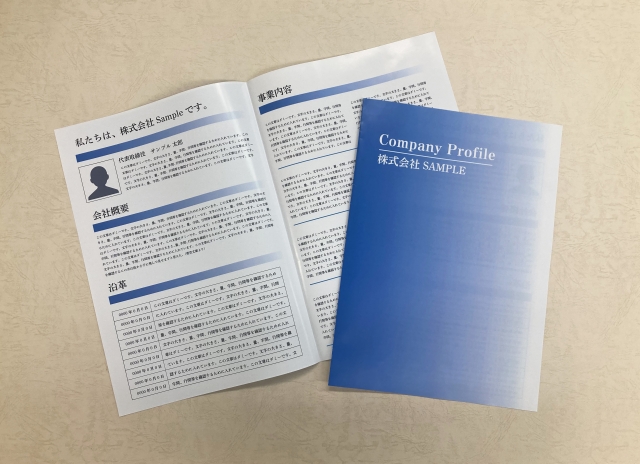情報の扱い方が、記憶の残り方を変える
情報化社会の現在、私たちはかつてないほど多くの情報を日々扱っています。メール、チャット、PDF、クラウド文書。気づけば日常の大半がデジタルで回っている。にもかかわらず、ふとしたときに、「あの時のメモ、紙に書いたやつだったな」と記憶していることがありませんか?
紙とデジタル。どちらも「情報を記録する手段」には変わりありませんが、私たちの脳に残る“記憶の残り方”には、確かに違いがあるように感じます。本稿では、紙とデジタル、それぞれの情報との向き合い方の違いから、なぜ“記憶に残る密度”が変わるのかを探ってみたいと思います。
今回は、紙とデジタルの「記憶の残り方」の違いについていくつかご紹介します。
書くという「身体性」が記憶を定着させる
紙に手で文字を書くという行為には、独特の“身体性”があります。ペンの重み、紙の手触り、インクの濃淡。書くスピードや筆圧の変化は、そのまま感情や思考の動きと結びついています。
この身体性が脳の記憶プロセスに与える影響は、多くの研究でも明らかになっており、「手書きで書くことは、単なる記録行為以上に、脳内の整理や記憶の定着に寄与する」とされています。特に、重要なアイデアや、自分自身の感情が動いた瞬間を記した紙のメモは、「どのノートのどのページに書いたか」「どのときに何を感じていたか」という文脈と一緒に脳に刻まれます。
つまり、紙に書くという行為は、情報を“覚えさせる”というより、“忘れられない形で体験させる”のです。
デジタルは“覚える”より“探せる”ことが強み
一方で、デジタルは圧倒的な利便性と検索性を誇ります。手書きのノートをめくって探すよりも、キーワード検索で瞬時に情報へアクセスできる。そのため、私たちはデジタル上の情報に対して、「記憶する」より「すぐに引き出せるようにする」という意識で接するようになります。
この“検索前提”の感覚が、記憶の残り方にも影響を及ぼします。つまり、「あとで見返せばいい」「探せばすぐ出てくる」と思う情報ほど、脳に深く刻まれにくくなるのです。逆にいえば、情報を探す行為そのものが習慣化しており、“記憶に残る必要性”が薄れているとも言えます。
とはいえ、これはデジタルの弱点ではなく、“思考のスタイルが違う”というだけの話です。必要な情報をいつでも再現できることは、紙では到底実現できないアドバンテージでもあります。
「記憶に残す」か「記録として残す」か
紙とデジタルの一番の違いは、“記録の目的”のあり方にあるのかもしれません。紙に書くとき、私たちは自然と「覚えておきたい」「忘れたくない」という気持ちを込めていることが多い。自分の思考の流れや感情の動きを記しながら、「思いを紙に残す」という姿勢で情報と向き合っています。
一方デジタルでは、「あとから他人と共有する」「チームで検索・利用する」という“外部との接続”を前提に書かれることが多くなります。ここで重視されるのは、“自分が覚えておくこと”よりも“誰もがアクセスできること”。だからこそ、記憶よりも整備、感情よりも構造化が優先される傾向があります。
図面スキャン・電子化のお悩み解決致します!
お気軽にご相談下さい!
ご相談・お見積りは無料です! 物量が多い場合は、
現地見積にお伺い致します!
019-643-8481
電話受付時間 9:00~18:00
( 土日祝除く )