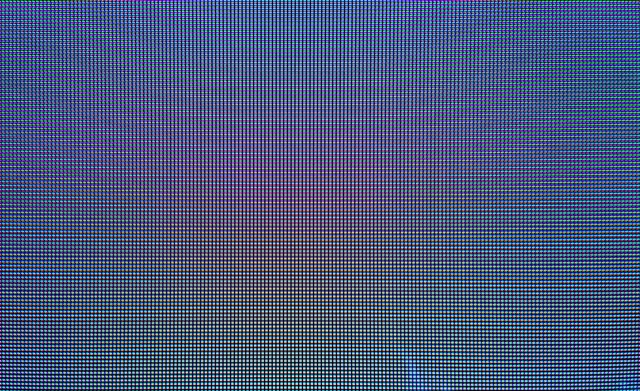モアレ現象とは何か──目に見えない“干渉”が生む模様の正体
スキャンした写真や印刷物に、不思議な縞模様や波のようなパターンが現れたことはないだろうか。意図せず入り込むその模様は、「モアレ(moiré)現象」と呼ばれる。名前は耳慣れないが、私たちの身近なスキャン作業や印刷の中でよく起きている現象だ。
モアレ現象は、2つの周期的なパターン(格子やドットなど)が重なったときに生じる視覚的干渉だ。たとえば、新聞や雑誌の写真は、実は肉眼では見えにくい細かいドット(網点)で構成されている。スキャナがこの網点を読み取る際、その読み取り解像度や角度によって、網点とスキャナのセンサー配列が干渉し合い、結果として“実際には存在しない模様”が生まれてしまうのだ。
今回は、モアレ現象についていくつかご紹介します。
なぜスキャンでモアレが出るのか──デジタルと印刷の“解像度の戦い”
モアレ現象は、特に雑誌・カタログ・新聞などのオフセット印刷物をスキャンする際に顕著に現れる。これは、印刷物が「網点(スクリーントーン)」という非常に細かい点の集合で画像を表現しているためだ。スキャナは一定間隔で画像を読み取るデバイスだが、この間隔(解像度)と印刷の網点の間隔がズレたとき、両者が周期的にぶつかり合い、干渉模様が発生する。特に、スキャナの解像度が中途半端な場合(300dpiや600dpiでの雑誌スキャンなど)に発生しやすい。
つまり、モアレとは「解像度同士の戦いの副産物」であり、アナログとデジタルの間に横たわる“翻訳の誤差”とも言える。高精細な印刷物ほどモアレが目立ちやすく、デジタル技術の限界を感じさせる瞬間でもある。
どうすれば防げるのか?──モアレ対策の技術と知恵
モアレ現象は見た目に煩わしく、特にデザインや資料作成の現場では大敵だ。では、どうすればこの現象を回避できるのか。実は、いくつかの有効な対策がある。
1つは、スキャナの「デスクリーニング」機能を使うこと。これはスキャン時に自動的にモアレを抑える処理で、多くのスキャナに搭載されている。また、解像度を変えるのも手だ。300dpiではモアレが出たのに、600dpiや240dpiでは軽減されることがある。要は、網点とスキャナの間隔を“ぶつからないように調整する”のだ。
さらに高度な方法としては、Photoshopなどでぼかし処理を入れてから再度シャープネスをかけるテクニックもある。これはプロのグラフィックデザイナーがよく使う方法だ。技術の力とちょっとしたコツがあれば、モアレはかなり軽減できるのである。
見えてはいけないものが見える?──モアレ現象の美学と偶然のアート
興味深いのは、モアレが単なる“エラー”ではなく、時として意図的なアート表現として使われることだ。幾何学模様が波のように変形する様子は、独特の美しさを持ち、視覚的に非常に刺激的でもある。
実際に、現代アートや広告デザインの中には、あえてモアレ効果を使った作品が存在する。2枚の透明フィルムに模様を描いて重ねる「モアレアニメーション」や、動かすことで柄が動いて見えるインタラクティブアートなど、モアレは“偶然を操るデザイン”として注目されている。
こう考えると、スキャンで発生するモアレも、単なる失敗ではなく、デジタルとアナログの接点に生まれた“無意識のアート”と捉えることもできるのかもしれない。技術のズレが生んだ偶然が、人の目を楽しませる不思議──それもまた、モアレの魅力の一つである。
図面スキャン・電子化のお悩み解決致します!
お気軽にご相談下さい!
ご相談・お見積りは無料です! 物量が多い場合は、
現地見積にお伺い致します!
019-643-8481
電話受付時間 9:00~18:00
( 土日祝除く )